死亡届は葬儀屋に任せる?代行サービスの選び方と注意点
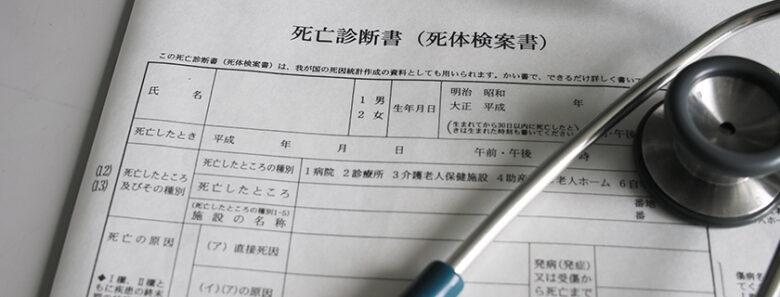
大切な人を亡くし、深い悲しみに暮れる中で、死亡届の提出をはじめとする煩雑な手続きに直面するのは、大変な負担でしょう。この記事では、死亡届提出にまつわる実務的な知識や、葬儀屋に依頼する際の選び方のポイント、トラブル防止のための心構えなどを詳しく解説します。
死亡届とは何か
死亡届の定義と法的位置づけ
死亡届とは、人が亡くなった際に提出が義務付けられている法定の届出書類のことを指します。戸籍法によって定められており、死亡の事実を知った日から7日以内(国内の場合)に、亡くなった人の死亡地または本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村に提出する必要があります。
この死亡届の提出によって、亡くなった方の戸籍が除籍され、官公庁による死亡の事実の確認と記録が行われます。また、死亡届の提出は、遺族年金の請求や相続手続きなど、死後の様々な法的手続きの基礎となる重要な届出でもあります。
死亡届提出の期限と必要書類
死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内(国内の場合)、または3ヶ月以内(国外の場合)と定められています。この期限を過ぎてしまうと、過料の対象となる可能性があるため、注意が必要です。
死亡届の提出に必要な書類は以下の通りです。
- 死亡診断書(または死体検案書)
- 死亡届書(A3サイズ)
- 火葬許可申請書
これらの書類は、医療機関や役所で入手することができます。記入の際は、記載事項に誤りがないよう十分に確認しましょう。
届出人の資格と役割
死亡届の届出人となれるのは、死亡者と同一世帯の親族や同居人などです。具体的には、以下の優先順位で決められています。
- 同居の親族(配偶者、子、父母、孫、祖父母など)
- 同居人
- 家主、地主、家屋・土地の管理人
届出人の主な役割は、死亡届への署名・押印と、役所への書類の提出です。実際の役所への提出は、届出人以外の代理人でも可能であるため、多くの場合は葬儀社が火葬許可の手続きと合わせて代行します。
死亡届の記入方法と注意点
死亡届の用紙は役所でも入手できますが、事前にダウンロードしてA3用紙に印刷しておくと、スムーズに記入できます。記入の際は、以下の点に注意しましょう。
- 死亡者の氏名、生年月日、死亡日時、死亡場所を正確に記入する
- 届出人の氏名、住所、死亡者との続柄を漏れなく記載する
- 死亡診断書(死体検案書)の内容と齟齬がないことを確認する
- 記載内容に誤りがないか、最後にしっかりと確認する
死亡届の記入に関して不明な点があれば、役所や葬儀社に確認し、適切に提出しましょう。
葬儀屋による死亡届代行サービス
死亡届の代行が可能な範囲
死亡届の提出は、本来、亡くなった方のご家族や同居人などの「届出人」が行うべき手続きですが、実際の役所への提出は代理人でも可能です。多くの場合、葬儀社が火葬許可の手続きと併せて死亡届の提出を代行しています。
ただし、死亡届への署名・押印は、必ず届出人自身が行う必要があります。この部分は代行できないため、葬儀社が代行サービスを提供する際も、届出人が署名・押印しなければなりません。
葬儀屋が提供する死亡届関連サービス
葬儀社が提供する死亡届関連のサービスには、以下のようなものがあります。
- 死亡届、火葬許可申請書などの必要書類の準備と記入サポート
- 役所への死亡届の提出代行
- 死亡診断書(死体検案書)の取得代行
- 火葬の予約
- 遺族年金などの各種手続きに関する情報提供とアドバイス
葬儀社によっては、死亡届の提出だけでなく、遺族年金などの死後の手続きに関する幅広いサポートを提供しているところもあります。
死亡届代行を依頼するメリットとデメリット
死亡届の代行を葬儀社に依頼するメリットは、何よりも手続きの負担を軽減できる点にあります。届出人の方は、故人との別れによる悲しみや喪失感を抱えながら、多くの手続きをこなさなければなりません。
そんな中、死亡届の作成から提出までを葬儀社に任せられれば、心理的・時間的な負担が大幅に軽減されるでしょう。また、書類の記入方法や必要な添付書類など、手続きに関する専門的な知識を持つ葬儀社のスタッフに相談できるのも大きな利点です。
一方、デメリットとしては、費用が発生する点が挙げられます。ただし、多くの葬儀社では、葬儀プランの一部として死亡届の代行を含めているため、追加費用なしで利用できるケースも少なくありません。
信頼できる葬儀屋の選び方
葬儀屋選びで確認すべき事項
信頼できる葬儀屋を選ぶためには、死亡届代行サービス以外の点も含めて、総合的に判断する必要があります。葬儀屋選びの際は、以下の事項を確認しましょう。
- 葬儀プランの内容と価格の明瞭性
- スタッフの対応力と専門性
- 施設の設備や衛生管理の状況
- 斎場や火葬場との提携関係
- アフターフォロー体制の充実度
実際に葬儀屋を訪れて、担当者と直接話をすることも大切です。その際は、要望に真摯に耳を傾け、柔軟に対応してくれるかどうかもチェックしましょう。
トラブル防止のための葬儀屋との契約
葬儀屋と契約を交わす際は、トラブルを防止するために、以下の点に留意しましょう。
- 提供されるサービスの詳細と料金が明記された見積書の入手
- 追加費用が発生する可能性がある項目の確認
- 万が一のトラブルに備えた、損害賠償責任の明記
- 個人情報の取り扱いに関する取り決め
契約書は必ず内容を確認し、疑問点があれば質問して納得してから署名しましょう。安心して葬儀を任せられる葬儀屋選びは、故人への最後の礼であり、遺族の方の心の負担を軽くする大切なプロセスなのです。
死亡届以外の重要な死後手続き
死亡に伴う行政手続きの概要
死亡届の提出は死後の手続きの第一歩ですが、それ以外にも期限が定められている重要な手続きがいくつかあります。遺族の方は、故人との別れの悲しみに暮れる中で、これらの手続きを滞りなく進めていかなければなりません。
死亡に伴う主な行政手続きには、以下のようなものがあります。
- 死亡届の提出(7日以内)
- 世帯主変更の手続き(14日以内)
- 国民健康保険の脱退手続き(14日以内)
- 年金関連の死亡届(国民年金は14日以内、その他は10日以内)
- 未支給年金の請求(5年以内)
- 葬祭費・埋葬料の請求(2年以内)
これらの手続きは、期限が法律で定められているため、注意が必要です。もし期限を過ぎてしまうと、各種給付が受けられなくなるケースもあるため、早めに取り掛かることが大切です。
銀行口座や不動産等の相続手続き
故人の財産を相続するためには、銀行口座や不動産等の名義変更手続きが必要です。相続手続きは、以下のような流れで進めていきます。
- 相続人の確定(法定相続情報一覧図の取得)
- 遺産の範囲と評価額の確定
- 遺言書の有無の確認・遺産分割協議(相続人間の話し合い、または調停・審判)
- 相続財産の名義変更手続き
相続手続きには期限は定められていませんが、早めに着手することが大切です。特に、預貯金の解約や不動産の名義変更には時間がかかるため、遺産分割協議は遅くとも葬儀後1~2ヶ月以内には行うことが望ましいとされています。
相続手続きは複雑で専門的な知識が必要なため、司法書士や行政書士等の専門家に相談することをおすすめします。円滑な手続きのために、遺族間のコミュニケーションを大切にしながら、適切なサポートを受けましょう。
死亡届トラブルを防ぐための心構え
よくある死亡届トラブルの事例
死亡届の提出時に、手続きの不備によってトラブルが発生するケースも少なくありません。
よくあるトラブル事例としては、届出期限を過ぎてしまい、過料の対象となってしまったというものがあります。突然の死への動揺から、届出の期限を失念してしまうことは珍しくありません。
また、葬儀屋への死亡届代行依頼時に、必要書類の準備が不十分だったため、手続きが滞ってしまったというケースも見られます。死亡診断書や火葬許可証など、役所への提出に必要な書類を事前に確認しておくことが大切です。
さらに、遺族間で死亡届の記載内容について意見が合わず、提出が遅れてしまうことも少なくありません。届出人の選定や、氏名の表記方法など、事前に遺族間で十分に話し合っておくことが求められます。
遺族間のコミュニケーションの重要性
死亡届のトラブルを防ぐためには、何よりも遺族間のコミュニケーションが重要です。故人を偲び、悲しみを分かち合う中で、次の点について話し合いを行いましょう。
- 葬儀の規模や形式
- 喪主や届出人の選定
- 死亡届や関連書類の記載内容
- 葬儀費用の負担割合
特に、死亡届の提出は法律で定められた期限内に行わなければならないため、早めに話し合いを始めることが大切です。遺族の方は深い悲しみの中にいるかもしれませんが、故人を送る大切な手続きについて、しっかりと向き合う必要があります。
話し合いの際は、葬儀社のスタッフなどに同席してもらうのも一つの方法です。第三者の視点から、公平なアドバイスをいただくことで、遺族間の意見の相違を調整しやすくなるでしょう。
葬儀屋との意思疎通を図るコツ
遺族の意向を汲み取り、適切なサポートを提供してくれる葬儀屋を選ぶことも、トラブル防止につながります。葬儀屋との意思疎通を円滑に行うためには、以下の点に気をつけましょう。
- 故人や遺族の意向をしっかりと伝える
- 葬儀や手続きに関する質問や不安は率直に相談する
- 費用や提供されるサービスの詳細を事前に確認する
- 万が一のトラブルに備え、契約内容を十分に確認する
葬儀屋選びの際は、実際に数社を訪問し、担当者と直接話をすることが重要です。要望に真摯に耳を傾け、柔軟に対応してくれる葬儀屋を選びましょう。
また、死亡届の代行依頼時には、必要書類や記載事項について、もう一度確認を行います。代行を任せきりにせず、遺族自身もしっかりと手続きに関わることが大切です。
まとめ
大切な人を亡くされた際に必要な死亡届の提出は、親族や同居人が行うことが原則ですが、実際の役所への提出は葬儀屋に代行を依頼することが一般的です。届出期限や必要書類などを理解し、遺族間でよく話し合いながら、信頼できる葬儀屋選びを行うことが大切です。故人を心を込めて送るためにも、死亡届手続きについてしっかりと理解を深めておくことが重要です。
監修 角田(株式会社葬儀のこすもす)
小さなお葬式は、神奈川県、東京都、北海道(札幌市)で、心のこもった家族葬をご納得いただける価格でご提供している家族葬専門の葬儀社です。
▶運営会社についてはこちら








