生活保護受給者の葬儀|利用できる制度と手続きの流れ
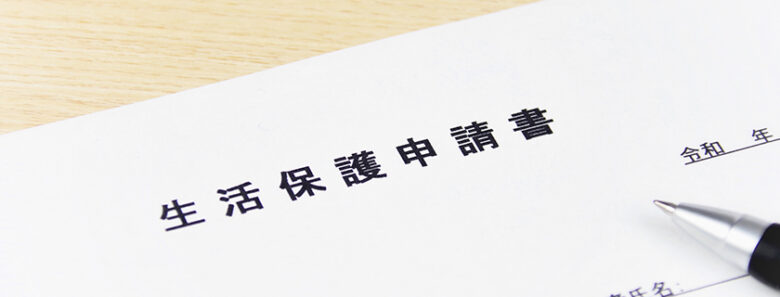
身近な人が亡くなり、いざ葬儀を執り行うとなると、負担となる葬儀費用の問題が切実にのしかかります。特に、故人や喪主が生活保護を受給している場合、経済的な事情が大きな課題になることも少なくありません。そこで活用できるのが、自治体からの支援を受けられる「葬祭扶助制度」です。本記事では、生活保護受給者の葬儀に関して利用できる制度や手続きの流れを分かりやすく解説し、その際に気をつけるべきポイントについて詳しくご紹介します。
生活保護受給者の葬儀の基本概念
生活保護受給者が亡くなった場合、残された遺族や喪主の負担を軽減する公的支援が存在します。ここでは、生活保護受給者の葬儀とは何か、その背景にある葬祭扶助制度の概要について押さえておきましょう。
生活保護受給者と葬祭扶助制度の背景
生活保護受給者とは、国が定める基準に照らして経済的に困窮し最低限の生活ができないので公的に不足額の支援を受けている人を指します。故人が生活保護を受けていた、あるいは喪主自身が生活保護を受給している場合には、葬祭扶助制度を利用できるケースがあります。
葬祭扶助制度は、火葬や遺体の搬送など、葬儀を行ううえで最低限必要な費用を行政が負担する仕組みです。必ずしもすべての費用がカバーされるわけではありませんが、申請が正しく認められれば費用負担を大幅に抑えることが可能です。なお、この制度を利用できるかどうかは、故人や申請者の資産・扶養状況など、いくつかの要件をクリアしている必要があります。
質素かつ最低限の葬儀
葬祭扶助制度による支給対象は、あくまでも「火葬を中心とした簡素な葬儀」に限られます。具体的には、直葬(火葬式)のように通夜や告別式といった儀式的要素を省略し、火葬と遺体の搬送、必要な物品(棺・ドライアイスなど)に費用が充てられます。一方で、戒名や読経といった宗教儀式にかかる費用などは含まれません。
葬祭扶助制度を利用するための条件
生活保護受給者の葬儀にかかる費用を軽減できる葬祭扶助制度ですが、誰でも無条件に利用できるわけではありません。ここでは、葬祭扶助制度を利用するために必要な条件や申請における注意点を紹介します。
利用条件と支給要件
葬祭扶助制度を利用するには、大きく下記の条件を満たす必要があります。
- 故人が生活保護受給者である、または喪主が生活保護受給者であり、葬儀費用を負担できない状況にある
- 葬儀を行う前に葬祭扶助の申請を行い、福祉事務所から支給決定を受ける
- 扶養義務者に葬儀費用を負担できるだけの余力がないこと
特に申請のタイミングが重要で、葬儀の前に必ず手続きをしなければいけません。葬儀後に申請すると、原則として葬祭扶助は受けられませんので、注意が必要です。
申請時に用意する書類
葬祭扶助制度を利用するためには、一般的には以下のような書類が必要になりますが、自治体によって必要な書類が異なる場合があります。
- 死亡診断書あるいは死体検案書
- 遺族の収入証明書
- 遺族の戸籍謄本
書類不備があると審査が長引いたり支給が認められなかったりする場合があります。あらかじめ必要な書類を確認しておくことで、スムーズな手続きが可能になります。
生活保護の葬儀の具体的な流れ
葬祭扶助制度を利用した生活保護受給者の葬儀は、通常の葬儀とは申請手順や内容に違いがあります。ここでは、葬儀の大まかな流れをステップごとに解説します。
1. 福祉事務所への連絡と死亡診断書の提出
まず初めに行うべきは、福祉事務所へ故人の死亡を連絡することです。電話で連絡した後、福祉事務所に時間を確認し、直接出向くことが多いでしょう。死亡診断書もしくは死体検案書は必須書類となりますので、取得し次第早急に相談するようにしましょう。
2. 葬祭扶助の申請
福祉事務所で葬祭扶助の申請手続きを進めます。ここで重要なのは葬儀前に手続きを行うことです。多くの場合、火葬や遺体搬送などの基本的な費用をどの程度自治体が負担してくれるかが決定されます。
3. 葬儀社との相談と依頼
葬祭扶助の支給が認められたら、葬儀社と打ち合わせを行い、葬祭扶助制度を利用して葬儀を行うことを伝えます。葬祭扶助制度によって行える葬儀の内容は必要最低限のもので、通夜や告別式を省略する直葬が基本となります。あらかじめ決められた予算・プランを上回るような一般葬や盛大な宗教儀式は認められません。
4. 葬儀実施と火葬
決定されたプランに沿って葬儀を行います。主に、遺体の搬送→安置→納棺→火葬というシンプルな流れです。ドライアイスや棺など、必要最小限の物品費用が扶助対象となるため、注意しましょう。
5. 費用の支払い
葬儀社への支払いは、自治体から直接行われます。喪主の一時的な立替は必要ない場合が大半ですが、自治体と葬儀社の取り決め内容をしっかり確認しておきましょう。
扶養義務者がいる場合といない場合
生活保護受給者が亡くなった際、故人には扶養義務者が存在する場合があります。扶養義務者とは、一般的に親族(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)で経済的に故人を支えられる可能性がある者を指します。ここでは、葬儀における費用負担の考え方について整理します。
扶養義務者がいる場合
扶養義務者が存在し、かつ経済的に余裕がある場合は、葬儀費用を扶養義務者が負担するのが原則です。しかし、実際には扶養義務者がいても経済状態が厳しく、支払いが難しいことも考えられます。そのような場合は、福祉事務所が「支払い能力がない」と判断すれば、葬祭扶助制度が適用されることがあります。
扶養義務者がいない場合
故人に親族が存在せず、喪主もいない場合は、家主や民生委員、あるいは自治体が代行して葬儀を行うケースがあります。ただし、生活保護のケースでも、まずは親族の有無を徹底的に調査し、誰もいないことが確定してから自治体が対応するという流れになります。
申請時期を逃したらどうなる?
生活保護の葬儀において最も重要とされるのが、申請のタイミングです。うっかり葬儀を先に行ってしまった、あるいは余裕がなく申請を後回しにしてしまった場合、どのような影響があるのでしょうか。
葬儀後の申請は原則不可
葬祭扶助は、葬儀前に福祉事務所に申請し、支給決定を受けてから実施しなければ認められない制度です。もしも順番が逆になり、既に葬儀を終えてしまった場合は、事後申請が認められないのが原則です。結果として葬儀費用を全額自己負担することになり、後から自治体に請求しても払い戻しは受けられません。
葬祭扶助が受理されなかった場合の対処法
福祉事務所の審査によっては、なんらかの理由で葬祭扶助が認められないケースもあります。ここでは、そんなときに取れる対処方法について解説します。
費用を最低限に抑える直葬プラン
葬祭扶助が認められなかった場合も、直葬や火葬式と呼ばれる簡素な葬儀を選択することで、費用を大幅に抑えられます。直葬とは、通夜や告別式を行わず、遺体を火葬場に直接搬送して火葬を行うシンプルな形式です。遺族の意向や宗教的理由で、葬儀に大がかりな儀式を求めない場合にも、この方法が利用されます。
自治体やNPO団体のサポート
葬祭扶助が使えないものの、経済的困窮が続いている場合は、お住まいの自治体やNPO法人による独自の支援が受けられるケースもあります。地域によっては、葬儀費用の一部助成や無償の遺体搬送など、さまざまなプログラムが用意されている場合がありますので、市区町村の窓口や福祉団体に相談してみるとよいでしょう。
葬儀後の遺品整理やその他の注意点
葬儀が終わって残されるのは、故人のお荷物や思い出の品々。生活保護受給者の葬儀では、遺品整理に関する補助制度が基本的に存在しません。こちらでは、遺品整理や自治体の対応についてまとめます。
遺品整理は親族が対応するのが原則
原則として、遺品整理は親族が行うのが通例です。葬儀同様、親族がまったくいない場合や、親族が高齢・病気などで対応できない場合は、行政やNPOなどに相談せざるを得ないこともあります。ただし、遺品整理にかかる費用や専門業者への依頼費用については、公的なサポートがない場合がほとんどです。
住民票の管轄と注意点
亡くなった方と喪主が別の自治体に住民票を持っている場合、どこで手続きするか分からなくなることがあります。原則的には喪主の自治体に申請します。まずは、喪主の住民票がある自治体の窓口に相談しましょう。
生活保護の葬儀に関するよくある質問
ここでは、実際に多く寄せられる疑問点や注意点について、Q&A方式でまとめています。
Q1. 一般葬はできないの?
葬祭扶助制度は、火葬や最低限の搬送などの費用を負担する制度です。そのため、華やかな雰囲気の通夜・告別式を伴う一般葬は、制度の対象外です。どうしても一般葬を希望する場合は、自己負担のみで実施しなければいけません。
Q2. 戒名や読経の費用は扶助される?
戒名を付けてもらうためのお布施や、読経を依頼する費用は、葬祭扶助の対象ではありません。宗教儀式にかかる費用は自己負担となるため、希望する場合は事前に宗教者と相談する必要があります。
Q3. 香典を受け取ったら報告義務はある?
香典は収入認定として扱われる場合がありますが、個人の葬儀における香典は必ずしも報告義務を課されるものではありません。ただし、香典返しにかかる費用は当然ながら葬祭扶助の対象にはならない点に留意しましょう。
Q4. 申請の手続きや書類はどこで確認できる?
市区町村の役所内にある福祉事務所で確認できます。自治体の公式ウェブサイトなどにも手続き方法や必要書類の一覧が掲載されていることが多いので、事前に下調べしておくと効率的です。
まとめ
ここまで、生活保護受給者の葬儀に関する制度や具体的な手続きの流れ、注意点について紹介してきました。葬儀をしっかり執り行うためには、行政とのやり取りだけでなく、早めの情報収集と申請が欠かせません。
- 葬祭扶助を受けられるかどうかは、故人や喪主の生活保護受給状況と扶養義務者の経済状態が大きく影響する
- 葬儀前に福祉事務所への申請を済ませないと、原則として葬祭扶助は受けられない
- 葬祭扶助制度を利用することで、直葬など必要最低限の葬儀費用がカバーされる
- 自己負担で読経やオプションの費用を支払うことはできない
- 遺品整理や香典返しなどの費用も葬祭扶助の対象外である
お住まいの自治体や福祉事務所を早めに確認し、正しい手順にのっとって手続きを行うことで、余裕をもって故人を送り出せるように準備を進めてください。
監修 角田(株式会社葬儀のこすもす)
小さなお葬式は、神奈川県、東京都、北海道(札幌市)で、心のこもった家族葬をご納得いただける価格でご提供している家族葬専門の葬儀社です。
▶運営会社についてはこちら








