葬儀に来てくれた方へのお礼の言葉と書き方とは?
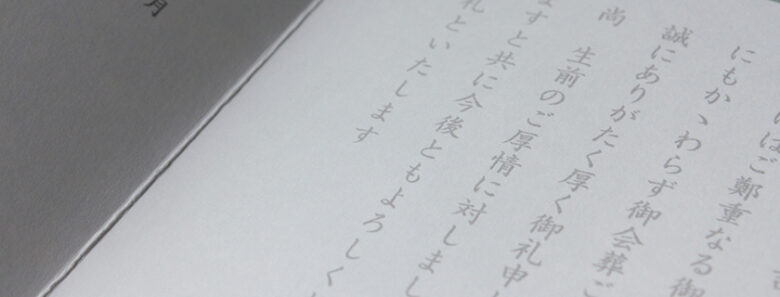
葬儀に参列してくださった方々への感謝の気持ちを表すこと、それは遺族にとって大切な務めです。ご多忙の中、時間を割いて会葬してくださったことへの感謝を伝えることで、参列者との絆をより深めることができるでしょう。しかし、葬儀の直後は遺族も混乱している時期。すぐにお礼状を送るのではなく、四十九日の忌明け頃まで落ち着いてから、改めて感謝の意を示すのがマナーとされています。
お礼状では、お礼の言葉と共に故人のお名前や戒名を記し、香典や弔電、お供え物を頂戴した方への感謝の気持ちを丁寧に綴ります。お礼状は手紙で送るのが基本ですが、文面は送る相手によって変えるのがよいでしょう。葬儀委員長へはお世話になった労をねぎらい、故人のお世話になった方へは別れを惜しむ思いを込め、主治医や病院関係者へは最期までの治療へのお礼と遺族の心境を吐露するなど、言葉を選んで真心を伝えたいものです。
そして、お礼状以外にも、お寺や葬儀会社、近隣住民、故人の勤務先関係者など、お世話になった方々へ直接お礼を伝える挨拶回りも忘れずに。形にとらわれるのではなく、故人への感謝を胸に、一人一人との絆を大切にしながら、お礼の気持ちを示していくことが肝要です。
はじめに
葬儀に参列してくださった方々への感謝の気持ちを表すことは、遺族にとって大切な務めです。ご多忙の中、時間を割いて会葬してくださったことへのお礼を伝えることで、参列者との絆をより深めることができるでしょう。本記事では、葬儀に来てくれた方へのお礼の言葉と書き方について詳しく解説します。
葬儀に来てくれた方へのお礼の重要性
葬儀に参列してくださった方々は、故人を偲び、遺族を支えるために時間を割いてくださいました。香典や弔電、お供え物を送ってくださった方もいるでしょう。こうした方々への感謝の気持ちを表すことは、遺族の務めであり、人間関係を大切にするためにも重要です。特に、高額の香典をいただいた方や、ご親族、故人の親しい友人などには、丁寧なお礼が求められます。
お礼状を送る意義とタイミング
お礼状を送る主な意義は以下の通りです。
- 参列者への感謝の気持ちを表す
- ご多忙の中、時間を作って会葬してくれたことへのお礼
- 会葬できなかった人へのお礼の意を示す
- 香典、弔電、お供え物を送ってくれた人への気持ちを伝える
- 高額の香典をいただいた人へのお礼
お礼状は、手紙で送るのがベストマナーとされています。メールやハガキは、親しい間柄の友人などの場合のみ許容されます。お礼状の送り時期は、四十九日の忌明け頃が適切です。葬儀直後は遺族も混乱しているため、すぐにお礼状を送るのはNGマナーとされています。落ち着いてから改めて感謝の気持ちを伝えましょう。
お礼状以外の感謝の伝え方
お礼状以外にも、感謝の気持ちを伝える方法があります。
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 挨拶回り | お寺や葬儀会社、当日お世話になった方々へ直接お礼を伝えます。近隣住民へは玄関先で簡潔に感謝の気持ちを伝えましょう。勤務先や故人の会社関係者へは、出社時や関係者を確認して挨拶します。 |
| 法要の案内状 | 四十九日法要や一周忌法要の案内状に、簡潔にお礼の言葉を添えるのも効果的です。改めて感謝の気持ちを伝える機会となります。 |
| お香典返し | お香典をいただいた方へのお礼の品を贈ります。品物選びは、相手の立場に合わせて心を込めて行いましょう。 |
葬儀に来てくれた方への感謝の気持ちを表すことは、故人を偲び、人間関係を大切にするために欠かせません。お礼状や挨拶回りなどを通して、丁寧に感謝の意を伝えましょう。マナーを守りつつ、真心を込めて対応することが肝要です。
お礼状の書き方
お礼状を送る相手の選定
お礼状を送る際には、まず送る相手をしっかりとリストアップすることが重要です。参列者全員はもちろん、僧侶・神主、葬儀社、知人・友人・親類で葬儀の手伝いをしてくれた人など、漏れがないように気を付けましょう。特に、高額の香典をいただいた方や、ご親族、故人の親しい友人などには、より丁寧なお礼が求められます。
お礼状の基本的な内容と構成
お礼状の内容は、以下の点を押さえておくことが大切です。
- 書き出しの言葉
- 参加や香典に対してのお礼
- 葬儀が無事に終了したことの報告
- 今後のお付き合いをお願いする言葉
- 書面でのお礼になってしまったことへのお詫び
- 結びの言葉
- 日付と喪主の名前
お礼状を書く際の注意点としては、時候の挨拶は不要で慣例的に省略されること、忌み言葉・重ね言葉は使わないこと、死や不幸を連想させる言葉は避けることなどが挙げられます。また、句読点は付けなくても問題ありませんが、付けても違反ではありません。葬儀を知らせていない人にはお礼状を出さなくてよく、気を使わせるだけなので基本的には不要です。
宗教・宗派に合わせた表現の使い方
各宗教・宗派によって用語が異なるため、注意が必要です。以下は、宗教・宗派別の主な用語の一覧です。
| 宗教・宗派 | 用語 |
|---|---|
| 仏教 | 御焼香、御布施、御読経、御法事、御法要、御戒名、御僧侶、御門徒、御本尊、阿弥陀様 |
| 神道 | 御玉串料、御祓い、御祝詞、御霊前、神様、神主様 |
| キリスト教 | 御ミサ、御献金、神父様、牧師様、教会、十字架、聖書、賛美歌 |
故人や遺族の信仰している宗教・宗派に合わせて、適切な用語を使うように心がけましょう。間違った用語を使ってしまうと、失礼にあたる可能性があります。不明な点があれば、葬儀社や僧侶・神主に確認するのがよいでしょう。
以上、葬儀に来てくれた方へのお礼状の書き方について解説しました。お礼状は、参列者への感謝の気持ちを表し、人間関係を大切にするために欠かせないものです。マナーを守りつつ、真心を込めて丁寧に書くことが大切です。また、お礼状以外にも、挨拶回りや法要の案内状、お香典返しなどで感謝の意を伝えることができます。故人を偲び、参列者とのつながりを大切にしながら、感謝の気持ちを伝えていきましょう。
お礼状の文例
拝啓
故 〇〇(故人の俗名)儀 葬儀に際しまして ご多用の中 御会葬いただき誠にありがとうございます 亡夫に代わりまして生前のお気遣いに御礼申し上げますとともに 今後とも変わらぬご指導を賜りますようお願いいたします 本来であれば 拝眉の上御礼申し上げるところ 略儀ながら書面をもちまして御礼のご挨拶とさせていただきます
敬具
令和〇〇年〇〇日
住所
喪主 〇〇(喪主の名前)
外 親戚一同
まとめ
葬儀に参列してくださった方々への感謝の気持ちを表すことは、遺族にとって大切な務めです。お礼状は、手紙で送るのがベストマナーとされ、四十九日の忌明け頃に送るのが適切です。お礼状には、故人のお名前や戒名を記し、香典や弔電、お供え物をいただいた方への感謝の気持ちを丁寧に綴ります。宗教・宗派に合わせた表現を用い、忌み言葉や不幸を連想させる言葉は避けましょう。お礼状以外にも、お寺や葬儀会社、近隣住民、故人の勤務先関係者など、お世話になった方々へ直接お礼を伝える挨拶回りも忘れずに。故人への感謝を胸に、一人一人との絆を大切にしながら、お礼の気持ちを示していくことが肝要です。
監修 角田(株式会社葬儀のこすもす)
小さなお葬式は、神奈川県、東京都、北海道(札幌市)で、心のこもった家族葬をご納得いただける価格でご提供している家族葬専門の葬儀社です。
▶運営会社についてはこちら








